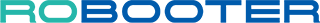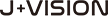はじめに
「シニアカーを使ってみたいけれど、価格が気になる…」そんな方にぜひ知っていただきたいのが、介護保険や自治体の補助制度です。
条件を満たせば、シニアカーや電動車いすの購入・レンタルにかかる費用の一部が助成されることがあります。今回は、シニアカーの補助制度の仕組みと申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。
——
シニアカーは介護保険で買えるの?
まず押さえておきたいのは、介護保険では基本的にシニアカー(電動カート)は購入対象外という点です。介護保険で支給される「福祉用具購入費」や「福祉用具レンタル費」は、歩行器・手すり・入浴補助具などの「自宅内の介助用品」が中心。
ただし、「電動車いす」や「電動三輪車」など一部機種は、要介護度や利用目的によってはレンタル対象となる場合があります。そのため、まずは担当のケアマネジャーに相談するのが第一歩です。
——
自治体による補助金・助成制度をチェック
介護保険で対象外でも、自治体独自の補助制度でサポートを受けられるケースがあります。たとえば以下のような制度が設けられている地域があります。
・シニアカーや電動車いすの購入費を一部助成
・機器のレンタル費補助
・免許返納者向けの優遇制度(購入費割引・クーポンなど)
補助の上限額は自治体によって異なりますが、3万円〜10万円前後の支援が受けられるケースもあります。
——
申請の流れ(一般的な例)
1.お住まいの市区町村役場へ相談
→ 高齢福祉課や介護福祉課などが窓口になります。
2.対象要件の確認 → 年齢、要介護認定の有無、免許返納の有無など。
3.申請書の提出と見積もり提出 → 購入前に申請が必要な自治体がほとんどです。
4.審査・交付決定 → 審査後、補助金額が確定。
5.購入・領収書提出・補助金振込 ※自治体によっては、「購入後の申請は対象外」となる場合があります。必ず購入前に確認・相談しましょう。
——
補助金の対象になりやすいシニアカーの条件
補助制度を利用できるのは、次のような条件を満たすモデルであることが多いです:
・公道(歩道)走行に適した設計である。
・最高速度が時速6km以下。
・安全装備(ライト・ウインカー・自動ブレーキなど)がある。
・国産または基準を満たすメーカー製品。
これらの要件を満たしているかどうかを示すひとつの指標が、TAISコード(福祉用具情報システム登録番号)です。TAISコードを取得している製品は、公的機関や介護事業者からの信頼性が高く、補助制度の対象として認められやすい傾向にあります。ROBOOTER J+VISIONは、このTAISコードを取得済みの正式登録製品です。安全性・品質・適法性の面で認められており、自治体の助成制度を利用する際にも安心してご検討いただけます。
——
ROBOOTER J+VISIONで安心・快適な外出を
ROBOOTER J+VISIONは、最新の電動モビリティ技術を採用した次世代型シニアカーです。軽量設計ながらも安定感があり、段差や坂道でも快適に走行可能。さらに、TAISコード取得による信頼性に加え、安全センサーや自動減速機能などの充実した機能を搭載。初めての方でも安心して使用できる設計です。補助金を活用すれば、よりお得に導入できるかもしれません。
▼ROBOOTER J+VISION 製品ページはこちら
https://www.jpstars.shop/shopdetail/000000000563
——
まとめ
・介護保険ではシニアカーは原則対象外
・自治体の補助制度を利用すれば費用負担を軽減できる
・申請は「購入前」に行うのが基本
・ROBOOTER J+VISIONは補助対象条件を満たす可能性のある安心設計モデル。補助制度を上手に活用して、快適で自由な移動生活をスタートしましょう。